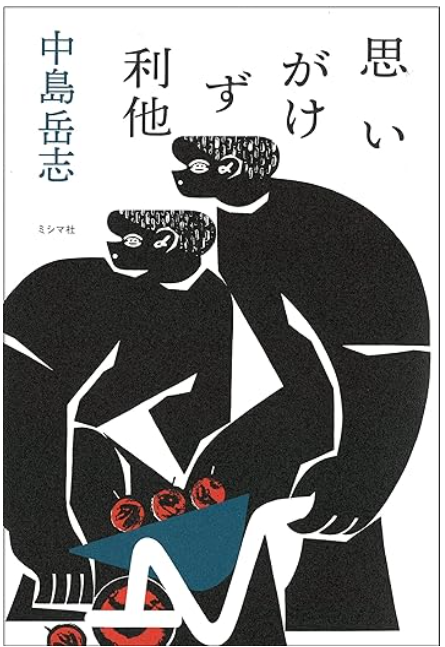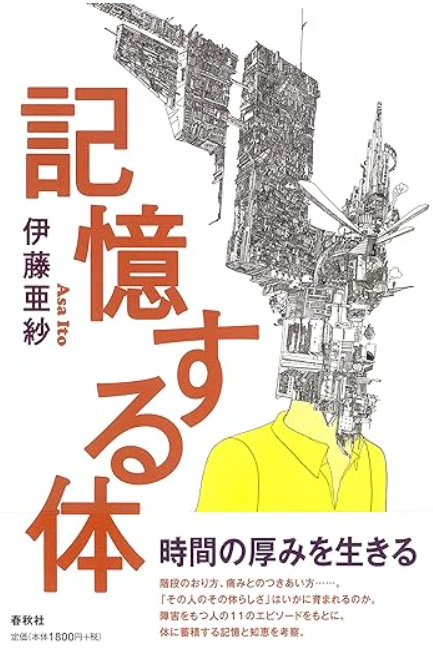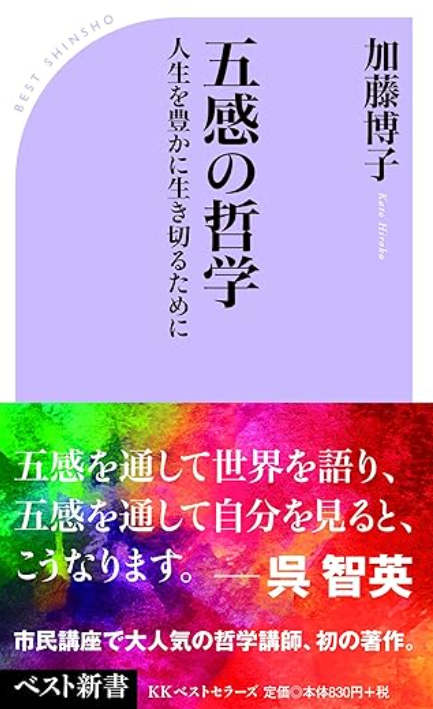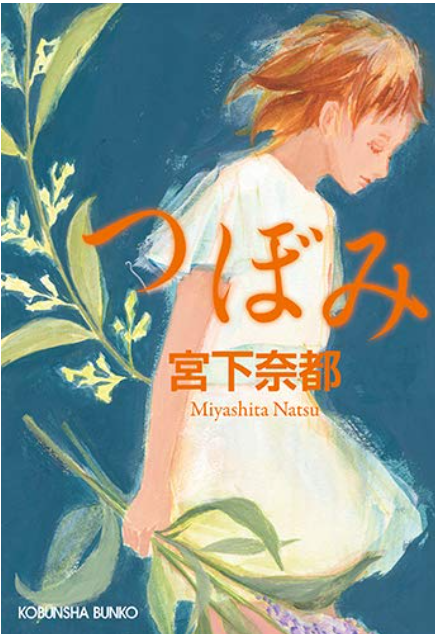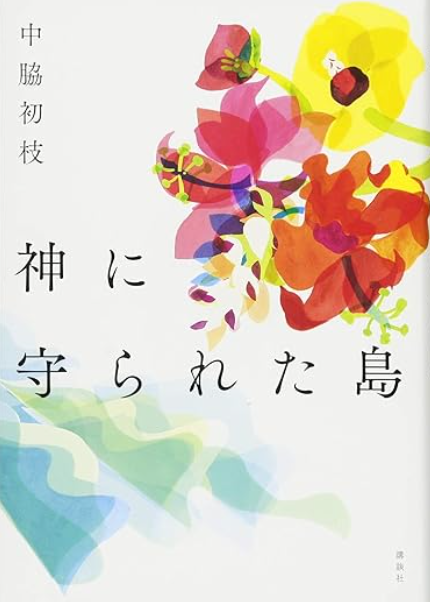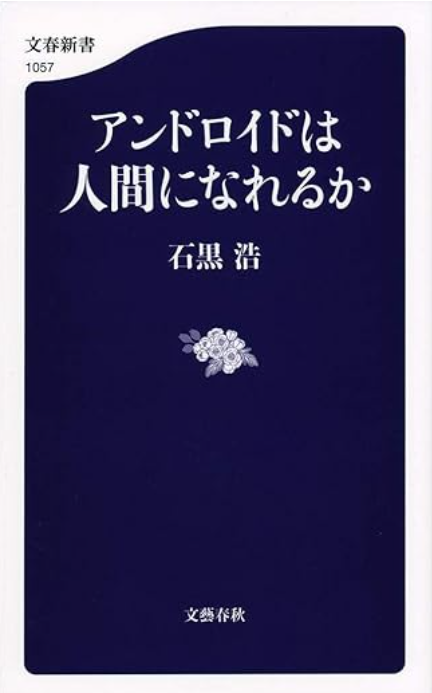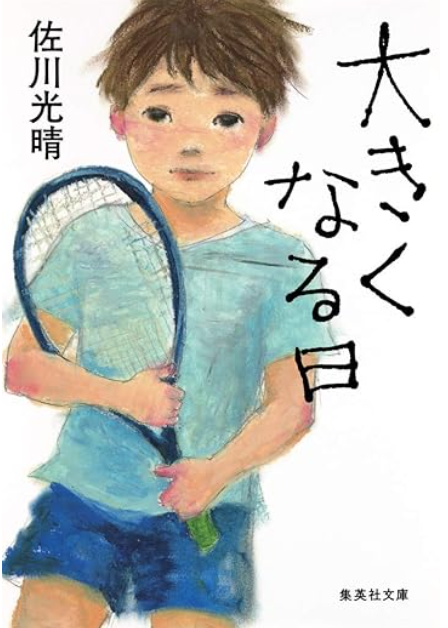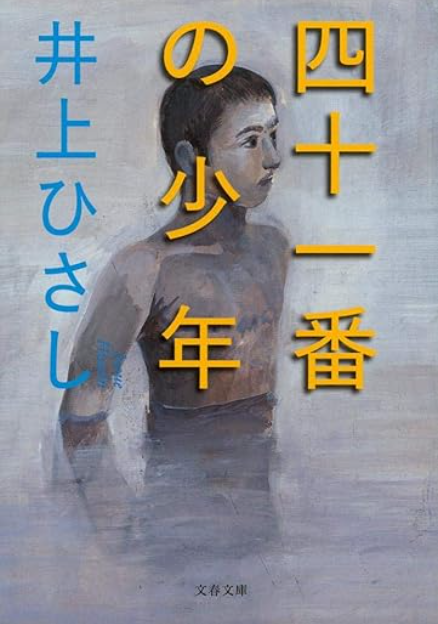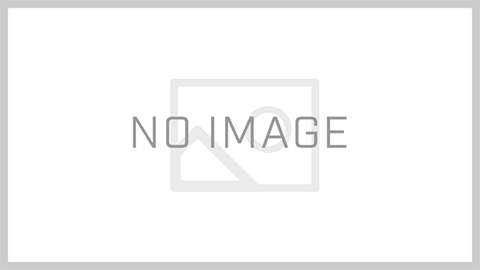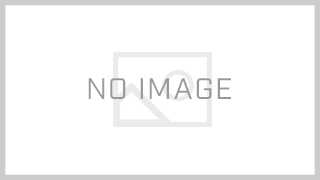東京の男子御三家の1つである武蔵中学校の国語を攻略する上でまずは重要になるのは、武蔵が受験生に対して「どの程度の読解レベルを求めているか」を把握することです。
学校側(=武蔵中)は「『本』を通して自発的に学べる受験生」を欲している一方で、受験生の多くは塾のテキストや模試で出題された「切り取られた読解文」のみを「受け身」で読んでいることが大半であるため、学校側が求めている読解レベルに届かずに「塾レベル」に留まっているケースが大半です。
この留まっている読解レベルを引き上げることが絶対的に必要ですが、塾が対策してくれるのは小6の夏休み以降の「学校別対策」が始まる頃と非常に遅いのが現状です。読解レベルは『少しずつ、着実に』というスタンスで段階的に引き上げていくことが必要なのに、入試まで残り半年の段階で急に読解レベルを上げようとするから、多くの受験生は着いて行くことができないんですね。
というわけで、塾に任せず、できるだけ早い段階から自らの努力で読解レベルを上げていく必要があります。
そこで有効なのが、というより、唯一の方法が「自発的に本を読むこと」です。
ただ、いたずらに読書をしても学校側が求める読解レベルよりも下のものを読んでいても読解レベルは上がらないので、オススメなのは武蔵中学校の入試で過去に出題された出典を読んでいくことです。
というわけで、今回は武蔵中学校の過去の出典を見ていきましょう。ざっと目を通しながら、「読解レベルを自らの力で引き上げるための初めの1冊」をぜひ探し出してみてくださいね。
武蔵中2024年度(令和6年度)の読解問題の出典
武蔵中学校の2024年度(令和6年度)入試では、以下の1冊から出題されました。
島木健作『随筆と小品』
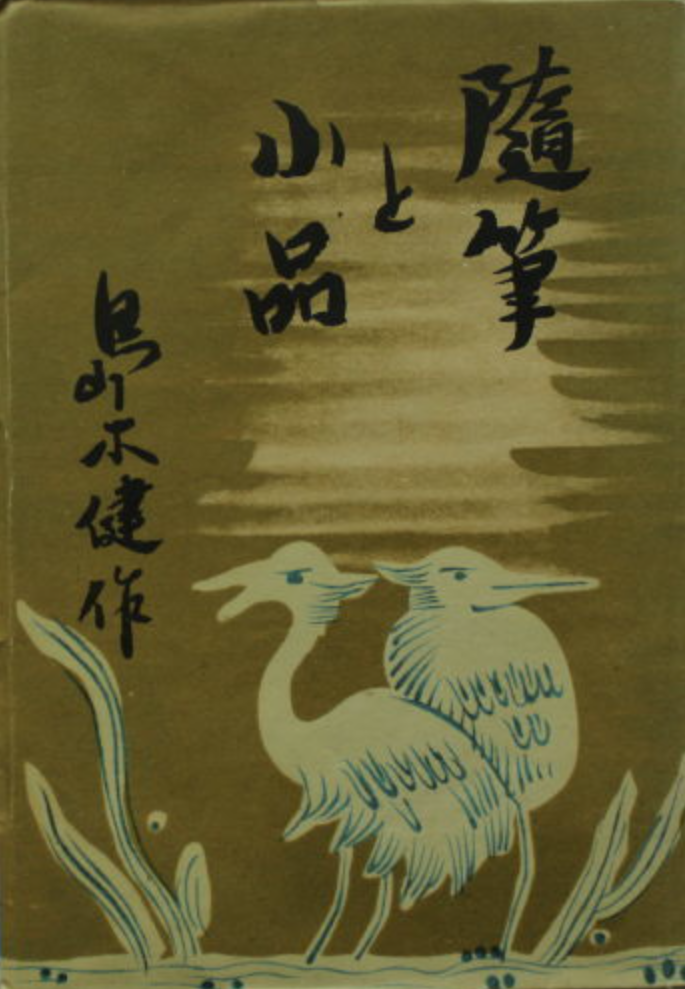
『随筆と小品』
(島木健作)
武蔵中2023年度(令和5年度)の読解問題の出典
武蔵中学校の2023年度(令和5年度)入試では、以下の1冊から出題されました。
中島岳志『思いがけず利他』
『思いがけず利他』
(中島岳志)
武蔵中2022年度(令和4年度)の読解問題の出典
武蔵中学校の2022年度(令和4年度)入試では、以下の1冊から出題されました。
伊藤亜紗『記憶する体』
『記憶する体』
(伊藤亜紗)
武蔵中2021年度(令和3年度)の読解問題の出典
武蔵中学校の2021年度(令和3年度)入試では、以下の1冊から出題されました。
加藤博子『五感の哲学』
『五感の哲学-人生を豊かに生き切るために』
(加藤博子)
武蔵中2020年度(令和2年度)の読解問題の出典
武蔵中学校の2020年度(令和2年度)入試では、以下の1冊から出題されました。
宮下奈都 『つぼみ』所収「なつかしいひと」
『つぼみ』
(宮下奈都)
宮下奈都さんの『つぼみ』は短編集で、2020年度の武蔵中ではこの『つぼみ』の中に収録されている「なつかしいひと」が出題されました。
ちなみにこの『つぼみ』、麻布中でも2020年度(令和2年度)に出題されており、その時は『つぼみ』所収の「まだまだ、」が出題されました。
武蔵中2019年度(平成31年度)の読解問題の出典
武蔵中学校の2019年度(平成31年度)入試では、以下の1冊から出題されました。
中脇初枝『神に守られた島』
『神に守られた島』
(中脇初枝)
武蔵中2018年度(平成30年度)の読解問題の出典
武蔵中学校の2018年度(平成30年度)入試では、以下の1冊から出題されました。
石黒浩『アンドロイドは人間になれるか』
『アンドロイドは人間になれるか』
(石黒浩)
武蔵中2017年度(平成29年度)の読解問題の出典
武蔵中学校の2017年度(平成29年度)入試では、以下の1冊から出題されました。
佐川光晴『大きくなる日』
『大きくなる日』
(佐川光晴)
武蔵中2016年度(平成28年度)の読解問題の出典
武蔵中学校の2016年度(平成28年度)入試では、以下の1冊から出題されました。
井上ひさし『四十一番の少年』所収「あくる朝の蝉」
『四十一番の少年』
(井上ひさし)
『四十一番の少年』は短編集で、この中に収録されている「あくる朝の蝉」が出題されました。
武蔵中2015年度(平成27年度)の読解問題の出典
武蔵中学校の2015年度(平成27年度)入試では、以下の1冊から出題されました。
長谷川櫂『和の思想-異質のものを共存させる力』
『和の思想-異質のものを共存させる力』
(長谷川櫂)
.
いかがでしたか?
読んでみたいと思える一冊は見つかりましたか?
.
ではでは、今回はこのあたりで。